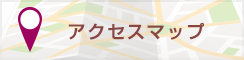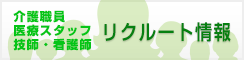緑ヶ丘療育園 ー お知らせ
てんかんミニ知識 第15回 フェニトイン(アレビアチン)を掲載しました。
フェニトイン(アレビアチン)は1940年に発売された古くからある抗てんかん薬で、昔はフェノバルビタール(フェノバール)と並んで非常によく使われていましたが、最近は下記のような理由であまり使われなくなりました。
通常、抗てんかん薬は投与量と血中濃度が相関する線形動態をとります。すなわち、投与量を増やすと増やした分だけ血中濃度が上がるので、投与量の調整がしやすいのです。ところが、アレビアチンは非線形動態のため、投与量と血中濃度が相関しません。したがって、アレビアチンの有効血中濃度である5~20μg/mlを維持するための投与量の調整が大変難しくなります。血中濃度をもう少し上げたいために、適当であろうと思われる量を増やしても全然血中濃度が上がらない場合がありますし、逆にほんの少量増やしただけで20μg/ml以上の中毒濃度に達してしまうこともあります。また、いったん有効血中濃度域に維持された後、投与量を変更していないにもかかわらず血中濃度が上がって中毒濃度になる場合がありますし、逆に有効濃度以下に低下してしまうことがあります。そのため、定期的にアレビアチンの血中濃度を測定することが必要となります。
アレビアチンの血中濃度が中毒濃度に達すると急性中毒症状としてふらつき、眼振、振戦などの小脳失調症状が出現しますので、おかしいと気付くのですが、重症心身障害児者では小脳失調症状の急性中毒症状に気付きにくいので、注意が必要です。アレビアチンを服用中の重症心身障害児者では急に嘔吐や眠気が出てきたときにはアレビアチンの急性中毒を疑って血中濃度を測定した方がよいと思います。
アレビアチンの慢性中毒では小脳萎縮が生じ、進行すると、ふらつきがでてきたり、転びやすくなったり、歩けなくなったりするので、そのような場合は頭部CTかMRIをとるようにします。しかし、重症心身障害児者では上記の症状がアレビアチンの慢性中毒症状とは認識されずに、年齢や基礎の病態によるものとしてとらえられてしまうことがあるかもしれません。急性中毒の小脳失調症状はアレビアチンの減量、中止により改善して元に戻りますが、慢性中毒の小脳萎縮は不可逆的です。
他の副作用としては、アレビアチンを長期に投与すると毛が濃くなりますし、歯茎が厚くなってきますので、美容上の問題がでてきます。また、てんかんミニ知識第14回テグレトールのところで記載しましたように、チトクロムP450という酵素の誘導による高脂血症や骨粗鬆症、薬疹、胎児への催奇形性の問題などにも注意が必要です。
以上のようなことから、アレビアチンを継続服用中の場合には、アレビアチンを止めて副作用の少ない新規抗てんかん薬に切り替えていくことが望ましいのですが、この切り替えはなかなかうまくいかないこともあります。
てんかん外来 皆川公夫
札幌緑花会 ロゴマーク
てんかん外来 臨時休診日のお知らせ
平成29年 9月29日(金) 終日
平成29年10月2日(月) 終日
平成29年 10月26日(木) 終日 ~ 10月27日(金) 終日
平成29年11月2日(木) 終日 ~ 11月3日(金) 終日
休診させていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほどお願い致します。
てんかんミニ知識 第14回 カルバマゼピン(テグレトール)を掲載しました。
カルバマゼピン(テグレトール)は部分発作の第一選択薬ですので使用頻度の高い抗てんかん薬ですが、発作型の診断を誤って小児欠神てんかんや若年ミオクロニーてんかんなどの発作に使用すると逆に発作が悪化しますので注意が必要です。
テグレトールは服用開始後10日目前後に薬疹が生じることがあります。そのため、担当医はテグレトールを開始する際には予め患者さんに10日目前後に発疹がでてその日のうちにどんどん広がる場合にはテグレトールによる薬疹の可能性が高いのですぐにテグレトールを止めて担当医に連絡するよう指導しておくことが重要です。もし、そのことを知らずにテグレトールを服用し続けると目や唇などの粘膜が真っ赤に腫れて、高熱が出て、皮膚も水ぶくれになったりする重篤なスティーブンス・ジョンソン症候群(皮膚粘膜眼症候群)に至る場合があります。テグレトールの薬疹にはヒト白血球抗原(HLA)が関係しており、漢民族ではHLA-B*1502、日本人ではHLA-A*3101が関連しているといわれています。
テグレトールは肝臓で代謝されますが、その際チトクロムP450という酵素を誘導します。このチトクロムP450酵素はコレステロールの合成にも関与しているので、テグレトールを服用しているとこの酵素が誘導されることによりコレステロールの値が高値になり、心血管系および脳血管系疾患のリスクが高くなることがあります。また、同様に骨代謝にも影響し、骨粗鬆症が起こりやすくなることもあります。ちなみに、グレープフルーツ(ジュース)はチトクロムP450を阻害するためテグレトールの血中濃度が高くなってしまうので、テグレトールを服用している人はグレープフルーツ(ジュース)を避けるほうがよいと思います。
テグレトールを飲み始めたら音が半音低く聞こえるようになったと訴える患者さんがいますが、絶対音感を持っている人が感じるようです。このメカニズムははっきり分かっていませんが、症状は1~2週間で消失することが多く、場合によっては少し量を減らすとすぐに正常な聞こえ方に戻ります。
他には、テグレトールにより抗利尿ホルモンの分泌異常(SIADH)が生じて低ナトリウム血症をきたすことがありますので、これにも注意が必要です。
テグレトールはナトリウムチャネルの急速な不活性化という作用機序により抗てんかん作用を発揮します。なお、1年前に発売された部分発作用のラコサミド(ビムパット)は他剤との相互作用がないので使いやすい薬ですが、ナトリウムチャネルの急速ではなく緩徐な不活性化というテグレトールとは少し違う作用機序のため、テグレトールとビムパットの併用は可能といわれています。
てんかん外来 皆川 公夫
緑ヶ丘療育園 敷地内禁煙のお知らせ
たばこが、喫煙者及びその受動喫煙者の健康を害し、肺がん等を誘発することから、平成15年5月に健康増進法第25条で病院等の受動喫煙の防止対策を講じるよう義務付けられ、緑ヶ丘療育園では施設建物内での禁煙を実施しておりましたが、患者様をはじめ皆様の健康をサポートするという社会的使命から、建物内のみならず、玄関、駐車場(車内での喫煙を含む)、通路を含めて施設敷地内を平成29年8月1日より全面禁煙とすることになりました。
この措置は、ご家族およびご面会の方々、タクシー運転手や業者の方々、施設職員すべての人が対象となっております。また、従来のたばこと同様に電子たばこ等の新しいたばこに関しましても敷地内全面禁煙とする姿勢に統一いたします。
より良い環境づくりのため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
緑ヶ丘療育園 院長 皆川 公夫
てんかんミニ知識 第13回 バルプロ酸(デパケン):その2を掲載しました。
女性にバルプロ酸(デパケン)による治療を行う場合にいくつかの注意点があります。
一つは食欲が亢進して太りやすくなるので、年頃の女性には大きな問題となります。ちなみに、トピラマート(トピナ)は逆に食欲が低下して痩せることがあります。
もう一つは女性が子どもを希望して妊娠を考える場合の問題点です。
てんかんミニ知識第2回に書きましたが、バルプロ酸を服用していると多嚢胞性卵巣症候群がおこる場合があります。多嚢胞性卵巣症候群になると、不妊症となって子どもが授かりにくくなってしまうことがあります。
一方、多嚢胞性卵巣症候群にはならずに無事妊娠した場合でも、葉酸が不足していたりバルプロ酸の1日服用量が多い場合には、胎児に神経管閉鎖不全が生じて脊髄髄膜瘤などの先天奇形を認めることがあります。脳と脊髄の基になる神経管は妊娠4週で形成されるので、妊娠がわかってから慌てて葉酸を服用したりバルプロ酸の量を減らしてももう手遅れなのです。ですから、子どもを希望する場合には計画的に妊娠する必要があります。
まず、妊娠3ヵ月以上前から葉酸0.4mgを毎日服用します。葉酸はドラッグストアにある葉酸サプリメントが1錠0.4mg(400μg)ですので、これを毎日1錠飲み続けます。
次に、主治医と相談してバルプロ酸を徐放製剤(デパケンRあるいはセレニカR)に変更し、さらに可能であれば1日量を600mg以下(できれば400mg以下)に減らします。バルプロ酸の1日量が1000mgを超えると神経管閉鎖不全による奇形が生じる確率が高くなるためです。また、母親が妊娠中に1日1000mg以上のバルプロ酸を服用していた場合には生まれた子どもの知能指数が軽度低かったという衝撃的な報告があったためです。
このようにバルプロ酸を服用している女性では妊娠に関して重大な問題があります。
そのため、若年ミオクロニーてんかんに代表される思春期発症のてんかん女性にはバルプロ酸ではなく、ラモトリギン(ラミクタール)やレベチラセタム(イーケプラ)を選択して投与する場合が多くなってきています。しかし、これらが無効の場合にはバルプロ酸を1日量400mg~600mgの低用量で投与することもあります。
また、乳幼児期からバルプロ酸を長期間続けている女性が妊娠可能年齢になった際には、担当医が上記の問題点をよく説明したうえで、バルプロ酸の量を減らしたり、バルプロ酸を他の薬剤に代えるなどの対応策を試みますが、なかなかうまくいかないこともあります。
いずれにせよ、このように妊娠可能年齢になったてんかん女性はバルプロ酸に関連する様々な問題点があることを十分認識しておくことが重要です。
てんかん外来 皆川 公夫
てんかんミニ知識 第12回 バルプロ酸(デパケン):その1を掲載しました。
バルプロ酸(デパケン)は全般発作(強直間代発作、欠神発作、ミオクロニー発作、脱力発作、強直発作、間代発作)の第一選択薬ですので、てんかん診療において非常に使用頻度が多い薬剤です。
特発性全般てんかんの小児欠神てんかんでは欠神発作に加えて強直間代発作もおこることがあるため、両方の発作に効くバルプロ酸を第一選択とすることが多いですし、若年ミオクロニーてんかんではミオクロニー発作と強直間代発作がおこることが多いので通常は両者に有効なバルプロ酸が選択されます。また、このような特発性全般てんかんだけでなく、ウエスト症候群、レンノックス・ガストー症候群、ドラベ症候群などの難治性てんかんにもバルプロ酸はよく使用されます。
バルプロ酸は半減期が短いので服用開始後2~3日で効果を確認できるというメリットがあるのですが、反面バルプロ酸は血中濃度の日内変動が大きいため日内変動を小さくするように工夫された徐放製剤(デパケンR、セレニカR)を使用することもあります。
バルプロ酸の有効血中濃度は50~100μg/mlですが、これを越えるような高血中濃度になると以下のような副作用が出てくることがあります。
バルプロ酸が高血中濃度になると血小板の数が少なくなることがあります。出血傾向が出るほど低下することはまれですが、10万/μLを割るようなときは投与量を減量して血中濃度を下げることが必要になります。例えば、ふだんの血中濃度が80μg/mlだったのにクロバザム(マイスタン)を併用したら、血中濃度が120μg/mlに上昇して血小板が10万/μL以下に低下したということがよくみられます。
また、いままでバルプロ酸の血中濃度が有効濃度内にあって月経が規則的だったのに、クロバザムを追加したら血中濃度が上がって月経が来なくなったという患者さんもいました。この場合もバルプロ酸の減量により血中濃度が元に戻ったら月経が来るようになりました。
さらに、バルプロ酸の血中濃度が高くなると血液中のアンモニアが高くなったり、カルニチンが低下したりすることもあるので注意が必要です。カルニチンについては前回の第11回のてんかんミニ知識で解説しましたので、参照してください。
次回はバルプロ酸:その2を予定しています。
てんかん外来 皆川 公夫
施設基準承認のお知らせ
平成29年2月1日より、「脳波検査判断料1」の施設基準が承認されましたので、今まで脳波検査時に算定していた脳波検査判断料2(180点)に代わり、脳波検査判断料1(350点)を算定することになりました。
てんかんミニ知識 第11回(てんかん診療におけるカルニチン欠乏)を掲載しました。
カルニチンは、脂肪酸からのエネルギー産生に必須の物質であるため、血中や組織内のカルニチンが欠乏すると、各臓器での脂肪蓄積、低ケトン性低血糖、高アンモニア血症、筋力低下、心筋症など様々な症状が出現し、生命に重大な影響を及ぼすことがあります。カルニチン欠乏に関連して、こどものてんかん治療においては3つのことに注意が必要です。
一つ目は抗てんかん薬のバルプロ酸(デパケン)です。デパケンはこどものてんかんによく使われる大変有効な薬ですが、デパケン投与によりカルニチンが低下することが知られています。しかし、血中カルニチンの測定は保険適用がされていないため、てんかん診療においてはカルニチンを測定することができないという問題点があります。ただし、デパケン投与中の血中アンモニア濃度とカルニチン濃度に負の相関がみられることがわかっていますので、6ヵ月毎の抗てんかん薬副作用チェックの際にデパケン投与中の場合にはアンモニアの検査も行い、アンモニアがきわめて高値の場合にはカルニチンが低下していると判断し、補充のためにカルニチン製剤(エルカルチンFF)を服用させています。
二つ目はピバリン酸(ピボキシル基)を含有している抗生物質です。フロモックス、メイアクト、トミロン、オラペネムなどでは長期服用によりカルニチンが低下することが指摘されています。短期間の投与では問題ないことが多いのですが、中耳炎などで数ヵ月にわたる長期投与によりカルニチンが低下し、重篤な症状を呈した症例が報告されています。とくにデパケン投与中の場合には抗生物質の種類に注意することが重要です。
三番目は重症心身障害があって経管栄養のみで栄養を管理している場合です。経腸栄養剤の中にはカルニチンが入っていないものや大幅に不足しているものもありますので、使用する経腸栄養剤のカルニチン含有量をチェックすることが必要です。とくにデパケン治療中の場合には要注意で、エルカルチンの補充が必要になることがあります。
以前はエルカルチンの処方の際には先天代謝異常症の病名が必要なため苦労した時代がありましたが、現在はカルニチン欠乏症の病名でOKになりました。これにならって、血中カルニチン測定もカルニチン欠乏の病名で一刻も早く保険適用されるようになることを望んでいます。
てんかん外来 皆川 公夫
てんかんミニ知識 第10回(抗てんかん薬と高脂血症)を掲載しました。
健康診断などで、総コレステロールが高い、悪玉コレステロールが高い、中性脂肪が高いと高脂血症を指摘され、薬を飲んだり、食事に気を使っている方がおられると思います。
私のてんかん外来で定期的に血液検査を行っている患者さんたちの中にも総コレステロールや中性脂肪が高い方がいます。ふとっている方もいますが、やせている方もいます。とりあえず食事指導を行いながら経過をみているのですが、比較的最近、テグレトールとアレビアチンによっても高脂血症がおこることがあるという情報をえました。
テグレトールとアレビアチンは肝臓で代謝されますが、その際チトクロムP450という酵素を誘導することが知られています。ところが、このチトクロムP450酵素はコレステロールの合成にも関与しているので、テグレトールやアレビアチンを服用していると、この酵素が誘導されることによりコレステロールの値が高値になると考えられています。アメリカの論文ですが、テグレトールかアレビアチンを服用している患者さんに対してテグレトールやアレビアチンをこの酵素を誘導しないイーケプラやラミクタールに変更したところ、総コレステロール、悪玉コレステロール、中性脂肪の値が有意に低下したと報告しています。
私の外来でテグレトールやアレビアチンを服用している患者さんで高脂血症の方はごく一部しかいませんし、これらの方の原因が必ずしも薬の影響かどうか断定できませんが、このようなこともあるという知識を持って対応していくことは重要と思います。
私は小児科医ですが、子どものときから診ていてすでに成人になっている患者さんたちもたくさん診させていただいていますので、テグレトールやアレビアチンで心血管系および脳血管系疾患のリスクが高くなることがあるという知見は衝撃的でした。
これからも長期間にわたるてんかん治療の場においては、いわゆる生活習慣病のチェックや対応にも真摯に取り組んでいかねばならないと痛感した次第です。
てんかん外来 皆川 公夫